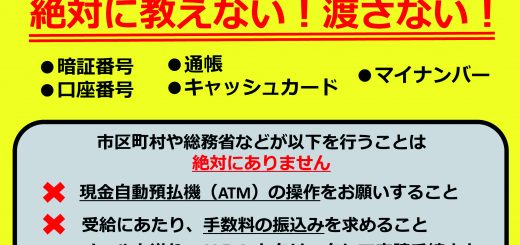本よみ松よみ堂
池井戸潤著『俺たちの箱根駅伝』
寄せ集めの連合チームが挑む箱根駅伝。魂の継走
「半沢直樹」「下町ロケット」など多くの作品で知られる池井戸潤が書いた箱根駅伝を舞台とした小説。今年の4月25日に出版された。初出は『週刊文春』2021年11月11日号~2023年6月15日号。ファンが長い「箱根ロス」に陥っているこの季節に一気に読んだ。といっても、この新聞が出る6月23日には全日本大学駅伝の関東地区選考会が行われる。そして、10月19日に行われる第101回箱根駅伝予選会までは4か月を切っている。
物語は予選会から始まる。明誠学院大学(架空の大学)は本選への出場が確実視されていたが、キャプテンの青葉隼斗(あおばはやと)の不調で11位に沈んだ。出場権は10位まで。10位の大学までのタイム差はわずか10秒だった。12人の選手が一斉にハーフマラソンの距離を走り、上位10人の合計タイムで争われる予選会。1人があと1秒ずつ削り出せば届く差だった。毎年、自衛隊の立川駐屯地をスタートし、立川の市街地を走り、昭和記念公園でゴールを迎える予選会では、この1人数秒という差で涙してきた大学の姿を何度となく見てきた。
一度はあきらめた箱根駅伝。しかし、隼斗には関東学生連合チームという形で箱根を走るチャンスが巡ってくる。この物語の主な舞台は学生連合チームなのだ。
学生連合チームは、予選会で敗退した大学の中から、タイムの良かった選手で構成される。ただ、予選会後につくられる急ごしらえのチームである上に、順位や記録は参考記録としてしか残らないため、モチベーションを保つのが難しく、いつも最下位あたりを走っている。
学生連合チームを率いるのは予選会11位の大学の監督、つまり明誠学院の監督だ。しかし、明誠学院を38年間率いてきた名将・諸矢久繁(もろやひさしげ)は突然勇退を発表し、OBの甲斐真人(かいまさと)に引き継ぐ。甲斐は箱根を走った名ランナーだったが、大学卒業後は一流総合商社に入社し、ビジネスの世界で成功を収めていた。長年陸上競技からは離れていて、監督の経験もない。明誠学院は箱根を連覇したこともある名門で、OB会も強い。この人事は現役の選手はもとより、OBを戸惑わせた。
甲斐は、連合チームで「三位以上」という高い目標を掲げる。
物語には、箱根常連校と言われる現実にある大学の他に、優勝候補の一角を担う東西大学と関東大学という2つの架空の大学が登場する。特に東西大学監督の平川庄介(ひらかわしょうすけ)は学生時代は甲斐のライバルで、マスコミを通して、連合チームを批判してくる。東西大学はこの物語のヒール役だ。
もう一つ、重要な舞台となるのが、箱根駅伝を生中継する大日テレビだ。チーフ・プロデューサーの徳重亮(とくしげりょう)とチーフ・ディレクターの宮本菜月(みやもとなつき)は、1987年1月2日の第1回の放送から守り続けられてきた選手と大会に対するリスペクト、真摯に向き合おうとする姿勢を貫こうとするが、編成局長の黒石武(くろいしたける)は番組にバラエティ色を持ち込み、視聴率を上げろと、いろいろと横やりを入れてくる。
不可能と言われた箱根山中を走る5区、6区の生中継を実現し、当日は系列局からの応援も入れて、千人ものスタッフが携わる箱根駅伝の生中継。そんな舞台裏も描かれる。
徳重たちは、1年をかけて各大学を取材するが、徳重たちでさえ、学生連合チームには注目していなかった。
記念大会となった今年の第100回大会には学生連合チームは編成されなかった。予選会の出場権を全国の大学に解放し、いつもより3チーム多い13校が本選出場を果たしたが、全て関東の大学で占められた。全国の高校の有力選手は箱根駅伝に出場できる関東の大学に集まる。関東ローカルな大会だが、箱根駅伝は実質全国大会と言っていい。10区間全てが20キロ以上という過酷なレースに対応できるだけの練習は簡単にできるものではない。地方の大学は、距離が短い10月の出雲駅伝と11月の全日本大学駅伝を目指すが、両大会でも上位は関東の大学で占められる。個人的には、関東以外の大学でつくる全国学生連合チームと、関東学生連合チームの2チームをつくればよかったのではないかと思っている。チームとしての出場が難しい大学には、連合チームでの出場を目指して練習している選手もいるからだ。
上巻では、不協和音もあった寄せ集めの連合チームの面々がそれぞれに箱根を走る意味を見出し、一つにまとまっていく姿と、大日テレビの徳重と菜月が様々な障壁を乗り越えて、大会本番を迎える姿が描かれる。
10章と最終章で構成される下巻は、10区間の連合チームの選手それぞれの戦いと、各選手の背景にあるドラマが描かれる。
箱根駅伝は給水係の選手・関係者にもドラマがある。
隼斗たちと10区間を走りながら、もう一つの箱根駅伝を観たような気がした。
【奥森 広治】
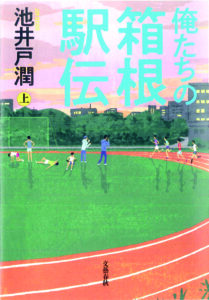

文藝春秋 各1800円(税別)