本よみ松よみ堂
奥山景布子著『フェミニスト紫式部の生活と意見』現代用語で読み解く「源氏物語」
紫式部が感じていた違和感。「源氏物語」に込めた真意とは
千年以上前から読み継がれてきた「源氏物語」の作者で、今年のNHK大河ドラマ「光る君へ」の主人公、紫式部とはどんな人物だったのだろうか。著者の奥山景布子さんは名古屋大学で古典文学研究の道に進み、その後、小説家として歴史小説などを発表している。
「源氏物語」は54帖(巻)からなり、第1帖「桐壺」から41帖「幻」までの主人公が光源氏。「幻」の後に光源氏の死を暗示する「雲隠」というタイトルだけで本文がない帖があり、42帖「匂宮」からは、光源氏の娘の子で第三皇子の匂宮と、世間的には光源氏の次男となっているが、実は父親が違う薫が主人公になる。
光源氏は帝の第二皇子だったが、母の桐壺更衣は3歳の時に亡くなり、「源」の姓を与えられ、皇室を離れた。貴族となった光源氏は様々な女性と関係を持つ。顔も覚えていない母、桐壺更衣への思慕から、初恋の相手は母にそっくりだと聞かされた年上の藤壺宮(藤壺は中宮。中宮や更衣は天皇の妻の呼称で、中宮の方が位が高い)。
光源氏の妻の中に紫の上という女性がいる。藤壺の姪で藤壺に生き写しのような容貌を持つこの女性は、まだ幼かった頃に光源氏に見染められ、略取(誘拐)され、光源氏によって「理想の女性」として育てられた。
「源氏物語」に最初に触れたのは高校の古文の授業だったと思う。ちょうどこの紫の上のエピソードのところが教科書に載っていて、「これって、犯罪じゃないの? マザコンでロリコン。なんか気持ち悪いなぁ」と思った。「源氏物語」は入試にも頻出する。基本的に文章に主語がなく、難解で、苦手だった。
小説家で自身も物語を書く立場の著者は、紫式部が書いた「紫式部日記」の記述なども参考にしながら、紫式部が「源氏物語」に込めた真意を考察してゆく。
第一講 「ホモソーシャル」な雨夜の品定め│平安の「ミソジニー」空間
第三講 ほかの生き方が許されない「玉の輿」の不幸│「シンデレラ・コンプレックス」からの解放
第六講 宮家の姫の「おひとりさま」問題│桃園邸は平安の「シスターフッド」?
第八講 「都合の良い女」の自尊心│花散里と「ルッキズム」
第九講 平安の「ステップファミリー」│苦悩する母たちと娘の「婚活」
いくつかのタイトルを抜き出してみたが、主に女性の登場人物の立場から、現代にも通じる問題を指摘している。
平安時代、第一に重んじられたのは漢詩。次が和歌。仮名主体の和文で書かれる架空の物語は「おんなこども」の娯楽扱い。「源氏物語」が評判になったからといって、紫式部が尊敬を集めたかどうか。「源氏物語」には漢籍の深い知識がふんだんかつ綿密に盛り込まれていて、著者は心躍らせるが、漢籍を読み、物語を書く女の姿は、「御幸ひは少なき」(幸が薄い)と、当時の一般女性の目からも評価されなかった。
著者が学んだ文学部の国文学研究室は圧倒的に女子が多いのに、院生になると、ほぼ男子ばかりという不思議な男女比。研究者になった著者は、研究会の発表の場でも男性の参加者からかけられる言葉に違和感を感じる。
「源氏物語」をちゃんと読んでいない私は、朝廷の貴公子・光源氏の恋愛を華麗に描く物語だとばかり思っていたが、光源氏を主人公にしながらも、光源氏礼賛の物語ではないようだ。30歳を過ぎたあたりからは意外にも明確に光源氏を拒絶する女性が現れるという。一方で、権力闘争の中で光源氏は天皇に近い身分にまで上り詰める。
働く手段が限られる当時の女性は、父親や後ろ盾となる親族を失うと、たちまち生活に困る。光源氏の傍には、こうした不安定な立場の女性が多い。光源氏に見捨てられれば、生きていけなくなるわけだ。パワーバランスがまったく違うわけで、この対等ではない人間関係の中での恋愛は、果たして「恋愛」と呼べるのだろうか。
本書は、紫式部が感じていた当時の「常識」に対する違和感や悔しさが、千年を超えて読み継がれる長編の物語を生み出す原動力となったことを感じさせてくれる。
【奥森 広治】
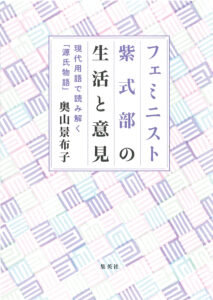
集英社 1800円(税別)





