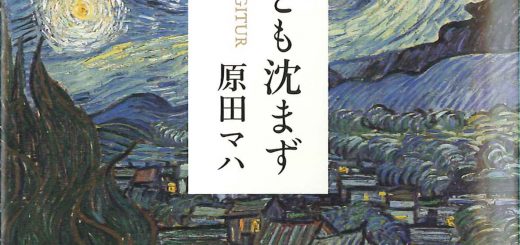本よみ松よみ堂
平野啓一郎著『本心』
舞台は2040年代の日本。主人公の朔也は亡くなった母のヴァーチャル・フィギュア(VF)を制作する。VFは人工知能(AI)が生前の母のデータをもとに学習し、本物そっくりに〈母〉を再現したもの。ヘッドセットを装着することで朔也は〈母〉と会話することができる。ただ立体的な画像であるため、触れることはできない。
未来の日本は今よりも格差社会が進んでいる。高校を中退し、30歳を目前にした朔也はリアル・アバターという仕事をしている。高齢で体が弱っているとか、何らかの理由で外出できない依頼者の代わりに旅行したり、買い物をしたりする。依頼者は朔也から送られてくる画像を見て実際にその場にいるような体験ができる。依頼者には富裕層が多かった。
依頼内容によっては危険や、嫌なこともあり、まだ社会的な偏見もある仕事で、長くは続けられない人が多いが、朔也はこの仕事が嫌いではなかった。依頼者に感謝されれば、やりがいを感じることもある。
生前の母からも一度「仕事」を頼まれたことがある。読書が好きだった母の依頼は川端康成の「伊豆の踊子」に出てくる滝を訪ねること。母に自分の仕事を理解してもらえるいい機会だと喜んだ朔也だったが、母から「自由死」したいという希望を唐突に告げられショックを受ける。この時代の日本は自分の死期を自分で選べることになっていた。母はまだ70前で、死に至るような病気に苦しんでいるわけではない。朔也は母の言う「もう十分生きたから」という言葉が理解できず、強く反発する。幼いころから母一人子一人の母子家庭で育った朔也にとって、母がいない世界というのは想像ができなかった。
しかし、朔也が母の「自由死」に反対している間に、母は不慮の事故で亡くなってしまった。喪失感の中で大金をはたいて、母のVFの制作を依頼した。
母が言った「十分に生きた」とはどんな意味だったのか。
母と仲が良かった同僚の女性・三好や、母と親しかったという老作家・藤原との出会いを通して、朔也は母の「本心」を探り、知らなかった母の実像や過去に触れることになる。
また、要人暗殺事件に関与したとして逮捕された同僚・岸谷、思いがけない出来事がきっかけで親しくなった大金持ちの青年イフィーなど、現代社会を彷彿(ほうふつ)とさせる登場人物も出てくる。
14章からなる作品の最終章のタイトルは「最愛の人の他者性」。この言葉には二重三重の意味が込められているような気がする。
母の同僚だった三好は朔也より少し年上でまだ若い。三好は仮想空間の世界に癒しを求めていた。三好の勧めで朔也は300億年の宇宙の時の流れを数分で体験するというアプリを体験する。一時的に私たちの肉体を構成している元素は死後再び別の肉体として再構成されるかもしれない。仏教にも通じる深遠な世界観だ。
この作品には簡単には消化できない様々な要素がぎゅっと詰め込まれている。
【奥森 広治】