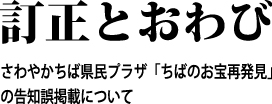本よみ松よみ堂
帚木蓬生著『花散る里の病棟』
福岡県の「町医者」四代、約一世紀にわたる物語
読み応えのある一冊だった。『小説新潮』2012年10月号から2021年8月号まで10年間に掲載された10編の短編を掲載順に収録している。福岡県の町医者、野北家の四代にわたる物語。著者も現役の医師とのことで、時にドキュメンタリーかと思われる筆致で胸に迫る。
初代の野北保造は、郷里の炭鉱町、N市で野北医院を開業し、山間部の山里で「虫医者」として多くの村人の命を救った。二代目の宏一の語りで描かれる「父の石」という一編で初めて知ったが、保造が医師として活躍した大正時代は寄生虫、特に蛔虫で命を落とすことも多かったらしい。衛生環境が悪かったのだろう。
野北家の医師としての家系は、実は二代目の宏一の代で途切れそうになる。宏一が中学生の時に父・保造が急死してしまうのだ。医師の道をあきらめかけた宏一だったが、志半ばで他界した父の思いを胸に、和裁・洋裁の仕事で家計をささえてくれた母の助力で、久留米の九州医学専門学校(現在の久留米大学医学部)を卒業し、内科医になった。同校は、軍医養成のために設立されたようなもので、外科医としての素養も身につけなければならなかった。宏一は卒業後間もなく軍医としてフィリピンに送られる。
戦争中にフィリピンに投入された日本軍兵力は約63万1千人。そのうち49万8千6百人が戦死した。太平洋戦争の日本人全戦没者の約4分の1にあたるという。武器・弾薬の補給もままならず、圧倒的な火力の差の中で、日本軍の司令部と兵站病院はフィリピンの島の中を転々とする。敵との戦いで、というより栄養失調と病気で亡くなる兵が多かった。「兵站病院」という一編には、その地獄が描かれている。日時が細かく記され、まるでドキュメンタリーを読んでいるようだ。
「復員」という一編は九死に一生を得て帰国した宏一が、命の恩人である上官の加藤軍医中尉の遺品と最期の様子を伝えるために、遺族を訪ねる話だ。「兵站病院」とは打って変わって、宏一の心の内が描かれる。
三代目の伸二は、内科医院に介護老人保健施設(老健)と特別養護老人ホームを併設している。伸二は両親と語らうように、老人たちと語らうことを楽しみにしている。実は短編は時系列ではなくランダムに並んでおり、最初の「彦山ガラガラ」は、この伸二の語りで始まる。「英彦山(ひこさん)」は、昔は「彦山」と書いたらしい。修験道の山である。彦山ガラガラはこの地方に伝わる土鈴(どれい)だ。
「胎(こ)を堕ろす」は伸二が患者の石崎米子さんという81歳になる元看護婦から聞いた話だ。日本に併合された朝鮮半島の赤十字病院の看護生徒だった石崎さんは、戦後、F町にある保養所に送られてくる女性たちの堕胎をしていた。戦地からの引き揚げの混乱の中で乱暴され、妊娠した女性たちだ。読んでいてもつらくなるが、伸二は父・宏一が戦場で見た地獄と重ね合わせながら石崎さんの話を聞く。
四代目の健は、アメリカで最新の肥満手術を学び、市立病院で勤務している。「歩く死者」という一編では、医学が進んだアメリカで、約2割強の人が健康保険に加入しておらず、治療法はあるのに、適切な治療を受けられずに死んでいく現実を目の当たりにする。
そして、最終章の「パンデミック」は伸二と健が直面する、現在も続く新型コロナウイルス禍だ。圧倒的に足りない検査、多額の予算を使った布マスクの配布に始まり、感染拡大の中で行われた旅行促進事業、ワクチン接種の遅れなど、政府の対策はちぐはぐ。一方で、勤務する市立病院は戦場のような忙しさだ。倒れる寸前まで働いている医療従事者に対して、その家族が差別されるという嫌な風潮も。昨年冬の第3派ぐらいまでが描かれている。
保造と伸二は九州帝国大学医科大学(現在の九州大学医学部)の出身だ。宏一が九州医科専門学校に進んだのは、経済的な事情もあったのかもしれない。そのため、軍医となり、戦場で辛酸をなめることになった。
四代にわたる医者の家を通して、明治の終わりから現代までの約一世紀にわたる時代を描いた壮大なストーリーだ。【奥森 広治】

新潮社 1800円(税別)