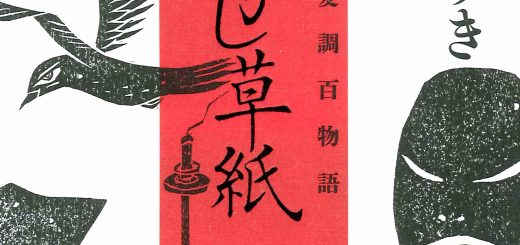巨大都市江戸を支えた大動脈
江戸川水運
前号で紹介した江戸川の開削の目的としては、江戸の水害防止、水運、新田開発、軍事的防衛の4つが挙げられているが、今回は近年の研究で有力視されている水運にスポットをあてて江戸川を見てみたい。【戸田 照朗】
川の定期航路の誕生
日本の海上交通は古代からずっと存在していたが、「定期航路」ができたのは、京都・大坂に豊臣政権、江戸に徳川幕府ができてからだという。
江戸時代が始まり、参勤交代が制度化されて、江戸には各大名の藩邸が建ち並ぶようになった。しかし、江戸にはまだ市場経済が成立しておらず、各藩は絶えず江戸に食糧を送る必要があった。
まだ陸上交通が整備されていない時代、人や馬での輸送には限界があり、重くてかさばる米俵を運ぶには、水上交通が一番効率がよくて便利だった。
江戸幕府が発行する金、銀、銅の通貨も体制が整うのは17世紀の後半になってからだったという。それまでは、地方では戦国大名が作った領国貨幣という独自の通貨が流通していた。幕府貨幣が全国貨幣となって領国貨幣の流通を停止できたのは、幕府が始まって100年後の元禄時代だったという。
各藩では、領国貨幣を江戸の金座や銀座で幕府貨幣に両替して必要な物資を購入していた。
一方で、江戸時代を通じて貨幣の代わりをしたのが米だったという。籾(もみ)は腐りにくく、誰にでも同じ価値を持ったので、物と物を交換する道具として便利だった。大名たちは食料としてだけでなく、販売米として大量の米を江戸に送っていた。
政治の中心となった江戸はやがて100万人の大都市として成長してゆく。
日本酒や呉服、紙や墨、筆などの高級品は江戸では作ることができず、良いものはみな上方(関西地方)から遠州灘を越えてくる南海路で運ばれた。消費者は武士などの富裕層である。
一方で、100万人もの人口を食べさせるための米や生活必需品を担ったのが関東平野の農村である。その輸送路として江戸川と利根川が整備された。
庶民だって酒は飲む。伏見や伊丹から送られてくる高級酒を富裕層が飲み、関東でもたくさん酒がつくられるようになって、庶民は関東産の安酒を飲んでいた。また、野田や銚子をはじめ、霞ヶ浦の土浦周辺にも醤油の一大産地ができた。
利根川水系の鏑(かぶら)川や神流(かんな)川、渡良瀬川や巴波(うずま)川、思川、鬼怒川など支流からも多くの物資が積み出され、江戸川を通って江戸に供給された。
逆に、江戸からの帰り船には全国から集められた優良品が乗せられて、関東農村に運ばれた。赤穂や才田の塩など瀬戸内海産の塩は江戸を経由して関東地方の農村に運ばれた。野田や銚子の醤油は江戸に運ばれただけでなく、関東の農村にも運ばれた。琉球産の砂糖は薩摩藩を通して江戸に出荷され、江戸から船で関東農村に運ばれた。
川の主役高瀬船
江戸川には、東北南部や関東地方の大名の船がひっきりなしに行き来していた。水戸藩は10艘前後の船を絶えず就航させていたという。「元文四年(1739)松戸町旅篭屋食売下女御尋につき一札」という史料によれば、武蔵、下総、常陸、上野、下野、出羽、奥州、信濃の8か国、50家以上の大名が江戸に荷物を送っていたという。
藩の船には2種類あり、藩が造った船と、農民の船で、特に立派な船を藩が雇いあげたものがあった。藩船には大名家の紋章を染め抜いた旗印が目立つように立てられ、他の船に分かるようにしていた。船の船頭は藩のお抱えで、士分格ということになる。藩の紋章の入った半纏(はんてん)や高張り提灯も支給されていた。
川船の主役は高瀬船で、大きなものは長さ25メートル、約800俵を積むことができた。船底が平底構造になっており、少ない水深でも大量に物資を輸送することができた。水深1メートルで航行出来たという。
高瀬船には「世事(せじ)」と呼ばれる船室があり、船頭・水主(かこ)3~5人が寝泊まりし、炊事をすることができた。大きさは3畳ほどだったという。
船の種類も様々で、高瀬船を筆頭に、ちょっと小ぶりな房丁高瀬船、上流部で使われた小鵜飼船や部賀(べか)船、高瀬船に似た細長い造りのヒラタ船や、渡り船には馬を乗せる馬渡船、川向こうの田や畑に向かうための作渡船、艀(はしけ)などがあった。屋形船などの遊興用の船や、船乗りたちが陸上の銭湯に行かなくても済むように船にお湯を張った湯船というのもあったという。
当時の河川水運は基本的に貨物船中心で、許可されている客船は限られていた。
しかし、茨城県境町からは毎晩夜行便が運航されていたという。会津藩など東北地方や北関東の武士や商人が境河岸まできて夜行便に乗れば、次の日の朝には江戸に着いていた。
利根川は江戸時代の初期に何度も付け替え工事をして造られた運河のためか、土砂の堆積が進み、ところどころに浅瀬ができて船の運航を妨げていた。天明3年(1783)の浅間山の大噴火で、大量の火山灰が降り、泥流となって利根川に流れ込んだことも一因だと考えられるという。
特に年貢米を運ぶ冬は好天続きで川の水位が下がる。そこで、中継基地として重要な役割を果たしたのが小堀(取手市)、関宿、松戸の3つの河岸だ。
500~1000俵という大量の年貢米を積んだ大型の高瀬船が、船底がつかえて動けなくなった時に、小堀河岸に待機していた多くの艀下(はしけ)船が出動して、水上で高瀬船から100俵とか150俵ずつ積荷を移して船団となって浅瀬を通った。積荷を軽くした高瀬船はその分浮かび上がり運行を続けることができた。
船団は関宿河岸で江戸川の水量を見て、水量が十分であれば、ここで再び高瀬船に積荷を戻した。しかし、水量が足りない場合は、松戸河岸まで来て、松戸河岸問屋の立会いのもと、積荷を戻した。河岸問屋は積荷を確認して証明書を発行し、艀下船は運賃をもらうことができた。加村や流山など、途中の河岸でむやみに積荷を戻すということはできなかった。必ず松戸まで来ることになっていたという。
幕末の嘉永年間に水戸藩お抱え船頭だった誉田(はんだ)嘉之助が4回分の航行日記を残しているという。
それによると、年貢米を満載して利根川を遡る時よりも、荷を下ろして江戸川を遡る帰りのほうが大変だったようだ。
後ろから風が吹いて、帆を張って川を遡れば楽だが、風が吹かないと、水主が船から下りて綱で船を引き上げたり、川底に竹竿を突き刺して進まなければならなかった。
嘉之助の日記によると、4回目の行程では、江戸川に入って8日かけてやっと関宿、境河岸に着いたという。
蛇行していて川幅も広い利根川に比べ、比較的真っ直ぐで川幅も狭い江戸川は風を受けるのが難しかったのではないかという。
重要拠点だった松戸河岸
近世の河岸には河岸問屋などの運輸機構を含めた運送機能、荷物を船に積み上げたり、積み下ろしたりする機能、荷物を保管する倉庫と問屋があった。
松戸河岸というのは総称で、具体的には3つの河岸があった。
最初にできたのは平潟河岸で、次に納屋川岸(なやがし)と、金町松戸関所を渡った渡船場のところに渡船場河岸があった。河岸は3つあったが、同時期に存在したのは2か所である。納屋川岸は上流にあるので「上河岸」、渡船場河岸は「下河岸」と呼ばれていた。納屋川岸には青木源内家があって河岸問屋を務めており、渡船場河岸には梨本太兵衛という河岸問屋、船問屋があった。
御城米(年貢米)の幕府の蔵までの距離と運賃を記した「関東御城米御運賃改書写」(元禄3年・1690)には百数十の河岸場が記されているが、江戸川筋では、西宝珠花、流山、金杉(松伏)、行徳の河岸の名が挙がっているが、松戸はない。当時はまだ重要な河岸ではなかったのだろうか。「元文四年(1739)松戸町旅篭屋食売下女御尋につき一札」という史料によれば、松戸河岸は旗本の高木筑後守・甚左衛門が地頭だった寛永3年(1626)に営業税(河岸役永)を払い始めたとある。
しかし、前回見たように、江戸川の開削は寛永12年(1635)着工、あるいは寛永17年着工とする説があり、この時にはまだ江戸川はできていない。寛永3年当時は松戸の前を流れる川は利根川本流だった。松戸の渡しは平安時代の『更級日記』に既に出てきているので、寛永3年に河岸があってもおかしくはない。
なお、図にある「分水川」は享保16年(1731)に幕府勘定吟味役・井沢弥惣兵衛の改修によって直線化された江戸川で、樋野口と平潟の間を流れているのが改修以前の江戸川。点線で描かれている古利根川(現中川の流れ)はこの時まで松戸で江戸川に合流しており、古い利根川の本流だった。
水運+陸送の鮮魚街道
物資の輸送には、水運に陸送を加えたものも登場した。
人口100万人を有した江戸では鮮魚も大量に消費され、房州から江戸湾にかけての房総沿岸は江戸への鮮魚の最も主要な供給地だった。奥州や銚子で水揚げされた鮮魚は、夏季(5~7月)は、船を「活船(いけぶね)=生けすが付いた船」にして、利根川から関宿を周り、江戸川に入って日本橋の魚市まで輸送するという方法をとった。川の水量が減り、船で運ぶことが難しくなる冬季(8~4月)は、利根川を「なま船」で布佐まで行き、鮮魚(なま)街道を通り、陸路馬の背に乗せて松戸まで運ばれ、松戸から再び船に乗せ、江戸川を経由して日本橋に運ばれた。
水揚げの早かった魚や、鯖などいたみやすい魚ははらわたを抜いて、ささの葉などでサンドイッチにして、籠や箱に詰めて送られた。また、鯛などは血抜きをして活けじめにして送られたという。
鮮魚は、水揚げから3日目の朝に日本橋の魚市に並ぶよう決められていた。3日目の朝売りに間に合わせるためには、2日目の夜には魚市に着いていなければならないが、間に合わない場合は、最悪でも3日目の午前2時までに着いていればいいことになっていた。
1日目の夕方に銚子を発ったなま船は、2日目の未明に布佐に着き、昼までに鮮魚街道で松戸に着く。ここから再び船に乗せ、夜までには日本橋の魚市に着いている。当初、松戸河岸はまだ十分整備されていなかったようで、船が調達できない場合もあり、夜間の通行を許可する松戸宿名主発行の木札を持って、金町から日本橋まで馬で運ぶこともあったらしい。
ここで鮮魚街道と呼んでいる布佐│発作│亀成│浦部│平塚│富塚│藤ヶ谷│佐津間│金ヶ作│松戸のルートが成立するのは元文3年(1738)頃で、以降明治30年代(1900年代)頃まで続いた。
鮮魚街道には、この布佐ー松戸ルートのほかに木下ー大森ー白井ー八幡ー本行徳ルートがあり、これが2大ルートで、他に布施ー流山、安食ー本行徳などの抜け道があった。木下ー本行徳ルートに対して布佐ー松戸ルートはもともとわき道的存在だったが、運送量では木下ー本行徳ルートを上回り、鮮魚運送の主役となっていく。布佐ー松戸は途中に宿場がなく、通し馬で一気に輸送できた上、距離も木下ー本行徳ルートよりも約2里短かった。
利権をめぐって、双方が勘定奉行所に訴えるようなトラブルも度々起きている。
徳川秀忠の夢・利根運河
寛永8年(1631)、当時大御所だった2代将軍徳川秀忠は、7月から「下総国小金の野山をほりとおさせ、下総・常陸・下野・奥州の舟路を近く通し、運漕にたよりあらしめん」と命じた。小金の下総台地を掘り割り、江戸と東関東、東北とを結ぶ舟運のための運河開削を計画したのである。しかし、間もなく秀忠の病気が悪化して沙汰やみとなり、計画は幻のまま終わった。
ある意味で、この幻の計画が実現したのが利根運河である。
運営は利根運河会社。設計はオランダ人の御雇い外国人技師デ・レイケとロウエンホルスト・ムルデルら。デ・レイケは内務大臣の技術顧問(事務次官級)を務めたという外国人技師としては破格の昇進をした人で、利根運河を調査、設計した。ムルデルは調査、設計、施工のすべてに関わった。明治21年(1888)に着工した工事を2年間指導したが、竣工式には出られず、任期切れで帰国の船上にいた。運河公園には、地元郷土史研究家らが昭和60年に建てたムルデルの顕彰碑が建っている。
長年川船が悩まされてきた浅瀬区間を通らずに済むように、江戸川岸の深井(流山市)と利根川岸の船戸(柏市)の間の下総台地を開削した8・5キロの運河。幅は水面で16メートル、深さは平均水位で1・6メートル。工事には延べ220万人が従事した大工事だったという。
運河の開通で、東京~銚子間は関宿廻りの旧ルートより約40キロ、時間にして約6時間が短縮されたという。
両川口には料金所が設けられ、客船宿など80軒を超える店が建ち並び、堤には3040本もの桜が植えられた。最盛期の明治24年には年間3万8000隻、1日平均103隻の高瀬船や外輪蒸気船が往来した。
外輪蒸気船「通運丸」第1号が登場したのは明治10年。42隻まで建造され、明治末年には東京~行徳間に1日11往復もあった。乗客を運ぶ船は蒸気船になっても、荷物を運んだのは高瀬船などの川船が主流だった。
しかし、自動車や鉄道など陸上輸送の発達で、水運は衰退し、昭和10年(1935)には1日20隻以下に落ち込んだ。たびたびの洪水で修繕費もかさみ、民間企業では経営を支えきれなくなり、内務省が昭和16年に買い上げるかたちで、その役割を終えた。運用されたのは、約50年だった。
現在の利根運河は洪水調整水路、また親水公園として整備されている。
※『江戸川の社会史』(同成社)の「近世江戸川の水運」(渡辺英夫)、「松戸河岸の成立」(小高昭一)、「特別展 川の道 江戸川」の図録(松戸市立博物館)の総説、『松戸市史 中巻』(松戸市)、『│魚を運ぶ道│利根川木下河岸と鮮魚街道』(山本忠良・崙書房出版)、『論集 江戸川』(「論集 江戸川」編集委員会編著・崙書房出版)の「お雇い外国人技師と利根運河」(新保國弘)を参考にしました。

松戸市立博物館に展示されている松戸の河岸復元模型

高瀬舟の模型。前方に「世事」がある(松戸市立博物館)



現在の利根運河