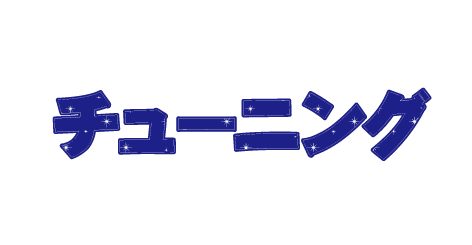松戸の文学散歩 旅人と松戸
古代の昔から交通の要衝だった松戸は、文学作品の中で登場人物が旅の途中で立ち寄った場所として度々登場する。特に平安時代に書かれた「更級日記」は、松戸の地名が「まつさと」として初めて文学作品に登場した例として知られる。今年は丑年だが、牛車(ぎっしゃ)にゆられての旅である。「旅人」に焦点を当てて、文学作品を紹介する。【戸田 照朗】
更級日記

「更級日記」の著者も渡った江戸川と松戸の中心市街地
「更級日記(さらしなにっき)」は、松戸が「まつさと」という名で初めて文学に登場した作品として有名だ。著者の菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)は寛弘5年(1008年)に生まれた。「更級日記」は、50歳を過ぎてから自分の人生を振り返って書いた自伝的物語とも言える。
著者は、10歳から13歳までを上総国(かずさのくに)で過ごした。当時の千葉県は房総半島の突端に安房国(あわのくに)があり、房総半島の大部分を上総国が占め、現在の松戸市など東葛地域は下総国(しもうさのくに)に含まれていた。
父・菅原孝標は、上総国の国司(こくし=地方長官)として赴任中で、著者は姉や継母(けいぼ)から様々な物語や光源氏(ひかるげんじ)のことなどを話してもらうのが唯一の楽しみだった。等身大の薬師仏を作ってもらい、1日でも早く都に帰って、物語の本を思う存分読めるように祈っていた。
念願かなって、13歳の秋に父の任期が終わり、都に帰ることになった。
出発は寛仁4年(1020年)9月3日。準備に手間取り、夕方になってから、願いを聞いてくれた薬師仏に心を残しつつ、牛車(ぎっしゃ)に乗り込んだ。この日は「いまたち」というところに急ごしらえの茅葺(かやぶき)の家をつくって泊まった。この「いまたち」に10日ほど滞在し、9月15日に下総国に入り、「いかた」に泊まった。17日早朝に「いかた」を出発。「まのの長者」という大金持ちの屋敷があったあたりが今は深い川になっており、門の名残だという4本の太い柱を見ながら船で川を渡った。その夜は「くろとの浜」というところに宿泊。
18日の早朝に出発し、下総国と武蔵国(東京都)の国境を流れる太井川(ふといがわ=江戸川)の船着場、「まつさと(松戸)」に着いた。「まつさと」に一晩泊まり、夜のうちに荷物を向こう岸に渡した。
一行の中には著者の乳母(うば)がいて、妊娠していたが、「まつさと」に来てから出産した。乳母の夫は最近亡くなっている。著者は、乳母が寝ている粗末な小屋を見舞うが、やつれて、月にうつる顔色は透き通るほど青ざめていた。産後すぐの旅は無理ということで、乳母は「まつさと」にとどまって養生することになった。
翌19日にはここまで一緒に来てくれた上総からの見送りの人たちも引き返し、涙、涙の別れとなった。
武蔵国に入った一行。都で衛士(えじ)をしていたこの土地の若者と姫宮(ひめみや)との伝説が残る竹芝寺では、地元の人に伝説を聞いて、それを紹介している。竹芝寺は、一説によると港区三田にある寺だという。
足柄山(あしがらやま。金太郎伝説で有名だが「更級日記」には金太郎の話は出てこない)の山中では、女旅芸人のグループに出会う。
富士山は著者が住んだ上総国からも見えていたが、近くで仰ぎ見て、その美しさに感動している。紺青の絵の具を塗ったような山肌に、1年中消えない頂上の白い雪という組み合わせは、私たち現代人にも馴染み深いものだが、今は夏季には雪が消えてしまう。やはり平安時代の方が気温が低かったのかもしれない。山の頂の平らな部分から火山の噴煙が立ち上り、夕暮れには赤々と燃えたつのが、はっきり見えたという。
遠江国(とおとうみのくに=静岡県西部)に入る手前で著者は体調を崩し、天竜川のほとりで何日か養生するなど、様々なことがありながら京の都に着いたのは出発から3か月後の12月2日だった。
京に着いた著者は早速いろんな手を使って、様々な物語や源氏物語全巻を手に入れて物語の世界に没頭する。
しかし、一方で悲しい出来事も続いた。著者の実母は京に残っていたが、上総国で優しくしてくれ、物語の世界にいざなってくれた継母が父と別れて家を出て行った。また、この年(1021年)は伝染病が流行しており、「まつさと」の渡りで別れた乳母が3月1日に亡くなった。「まつさと」に建てた粗末な小屋を見舞ったのが最期の別れとなってしまった。
屋敷に迷い込んできた子猫を姉と二人で飼っていた。著者は同年代で亡くなった侍従の大納言藤原行成の姫君に同情していたが、姉の夢に姫君が出てきて、猫は姫君の生まれ変わりだと言ったという。しかし、その猫も火事で死んでしまった。そして、姉も著者が16歳の時に産後に2人の子を遺して死んでしまった。
その後、著者は32歳で初めての宮仕(みやづか)えに出る。このころ、父は隠居し、母は尼になり、家のことは著者一人に任されていた。宮仕えにやる気を出し始めたころ、突然、両親の意向で辞めさせられ、キャリアは中途半端な形で終わってしまった。もともと両親は宮仕えに反対していた。
33歳で当時としてはかなり遅い結婚をした。息子を授かったが、51歳の時に夫に先立たれた。
著者の菅原孝標女は、学問の神様・菅原道真の血を引く家に生まれ、「蜻蛉日記(かげろうにっき)」を書いた藤原倫寧女(ふじわらのともやすのむすめ)が叔母にあたるという名門の出だが、豊かな貴族ではなかった。
国司になると収入が上がるため、父はずっと願いを出していたが、常陸介(ひたちのすけ)として再任官できたのは上総国から12年後の60歳の時だった。都の近くの国司を希望していたが、派遣されるのは再び遠国(おんごく)の常陸国(ひたちのくに)。今回は単身赴任で、あまりうれしそうではなかった。
著者の夫となった橘俊通(たちばなのとしみち)も父と同じような感じで、独身時代は物語の世界を追っていた著者も、やがて夫や息子の出世を第一に願うようになる。
どこか、現代を生きる女性にもつながる物語のように感じる。
思いをつぶやくように和歌を詠む。直接言えばいいものを、和歌に託す。格式の違いはあれど、メールかラインのようでもある。
原文は古文なので読むのに時間がかかるが、現代語訳版もいくつか図書館にあり、概略をつかむには、こちらがお勧めだ。
※参考文献=「21世紀によむ日本の古典4 土佐日記・更級日記」(森山京・著、小林豊・絵、ポプラ社)、「更級日記」(西下経一・校注、岩波文庫)
燃えよ剣

旧松戸宿(春雨橋付近)
東京の多摩地方の農家で育った土方歳三が、同郷の近藤勇らと京都で新選組を組織し、函館の五稜郭で戦死するまでを描いた司馬遼太郎の代表作のひとつ。
物語の終盤。幕府軍として参戦した鳥羽・伏見の戦で敗れた歳三たちは海路江戸に戻ってきた。そこへ幕臣から出た甲府100万石を抑えれば50万石を分け与えるという話。260年もの太平の世が続いた江戸時代。戦国の世のように力で国を切り取れるわけではない。近藤は大名になれると喜ぶ。幕府は5千両の軍資金を与え、砲2門、小銃500挺を貸与し「甲陽鎮撫隊」を組織させた。しかし、甲府へ向けて進軍を始めたはいいが、幸か不幸か、幼いころから慣れ親しんだ甲州街道を通る。新宿の遊女屋に泊まり、故郷の日野で歓待を受け、となかなか前へ進まない。そんな時、官軍がすでに上諏訪、下諏訪まで来ているという情報が来る。近藤はやっと腰を上げ、進軍を再開するが、時すでに遅し。土州(土佐)の板垣退助率いる官軍が先に甲府城に入ってしまった。歳三は神奈川の幕軍に援軍を頼みに馬を走らせるが、援軍を得ることはできず、近藤は勝沼で一戦を交えるが敗戦。50万石を与えるという話はどこまで本気だったのか。前将軍の徳川慶喜は上野寛永寺で謹慎恭順の態度を持していた。一説によると「甲陽鎮撫隊」は、慶喜の意を受けて官軍の江戸城攻撃回避を画策していた勝海舟が、薩長土から恨まれている新選組を江戸から追い払うために工作したものだという。
江戸まで落ち延びた彼らは、再挙を相談する。歳三の案は、下総でも富裕な地で、天領でもある流山で兵を募り、奥州(会津)へ行って戦う、というもの。ここで、意見が分かれ、新選組創設当初からのメンバーだった原田左之助、永倉新八は別行動をとることになった。新選組はもうないのに、同志である彼らに尊大な態度をとる近藤にはついていけないという気持ちもあったようだ。
剣は新選組屈指と言われる斎藤一ら隊士も合流。数日後、歳三は屯営の準備で先に流山へ行き、近藤は幕府の倉庫から集められるだけの銃器を流山に送り、幕府からは今回も2千両の金が出た。
近藤は馬丁の忠助に口を取らせ、3日目に出発。千住大橋をわたり、ほどなく松戸の宿へ。松戸宿は幕府開創以来の水戸街道の抑えの要衝で、御番を置いていた。江戸の消費地をひかえ、人口は5千人。繁華なものだった。
近藤が松戸宿に入ると宿場役人をはじめ、土地の者が50人ほどで宿場の入り口で迎えた。また、旅籠で昼食をとっていると、流山から迎えに来た200人ほどが、土間、軒下、街道に溢れた。賑やかなことが好きな近藤は、元気を取り戻した。これは歳三による手配によるものだった。
松戸から流山へ行く街道(流山街道だろうか)は狭く、馬が1頭やっと通れるほどの道で、両脇にタンポポが咲いている。山のない広い野で、田園のあちこちに榛(はん)の木が植わっていた。流山に着いた近藤は「長岡の酒屋」と呼ばれている屋敷に入った。
間もなく、官軍は流山に幕軍約300人がいることを察知する。「甲陽鎮撫隊」の頃から、近藤勇は大久保大和、土方歳三は内藤隼人という変名を使っていたが、甲府進軍の折、日野で近藤らを歓待した歳三の義兄にあたる日野宿名主佐藤彦五郎家を取り調べ、この流山駐屯の幕軍が新選組ではないか、というあたりを付けた。
官軍は利根川西岸(江戸川は長く利根川と呼ばれていたから、おそらく江戸川西岸だろう)に迫った。
「まだ奥州がある」と泣いて止める歳三の言うことも聞かず、近藤は官軍の求めに応じて、粕壁(春日部市)の本陣に申し開きに行くという。「賊名を残したくない」「大義名分を知っている」と。
この後、近藤は官軍に捕らえられ、板橋で刑死した。歳三は幕臣の大鳥圭介、榎本武揚らと合流し、東北、北海道を転戦した。函館の五稜郭の戦いで、歳三が戦死して6日後に降伏。大鳥、榎本らは後に赦免されて新政府に仕えた。
松戸宿で見せた歳三の近藤に対する気遣いには、副長として新選組という組織を作った手腕がうかがわれる。「昇り坂のときはいい、くだり坂になると人が変わったように物事を投げてしまう」という近藤の性格を見て、少しでも近藤の気分を良くしておきたかったのかもしれない。
松戸宿では旅籠で昼食をとっただけということになっているが、松戸シティホテル(センダンヤ)には、近藤勇が泊まったと伝えられている。センダンヤの創業は慶応4年(1868年)で、近藤が流山に向かったのは同年3月のことである。
近藤と歳三の別れの場所となった流山に屯所を置いた「長岡の酒屋」は今はないが、同地には酒類問屋の秋元さん宅があり、近藤勇陣屋跡の碑がある。江戸川河川敷には、近藤が敵陣に行くために渡った矢河原(やっから)の渡しの跡が残されている。
※参考文献=「司馬遼太郎全集 第六巻 燃えよ剣」(文藝春秋)、松戸関連の文学作品を探すため、宮田正宏さんの「松戸の文学散歩・私家版」を参考にしました。