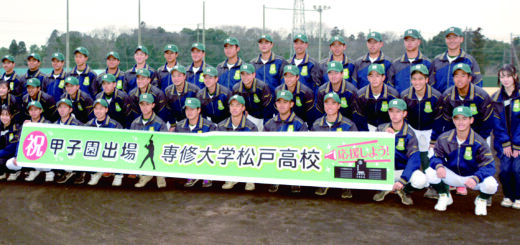本よみ松よみ堂
浅田次郎著『流人道中記(上・下)』

中央公論新社 各1700円(税別)
人が人を裁く不条理。現代にも通じる問いかけ
万延元年(1860)、旗本の青山玄蕃は、姦通罪で切腹を言い渡されたが、「痛えからいやだ」と言って、腹を切らなかった。青山家は旗本の中でも三河(家康の出身地)以来の名家で、腹を切らないなら打ち首というわけにもいかない。寺社奉行、勘定奉行、町奉行が顔を突き合わせ、ひねり出した妙案は、蝦夷福山の松前藩にお預けというものだった。つまり流罪である。押送人に選ばれたのは町奉行所の見習与力、若干19歳の石川乙次郎だった。
日光街道から奥州街道へ、2人の旅が始まる。当時の街道や宿場町の様子が旅情を誘う。
玄蕃が腹を切らなかったことで、お家は断絶。所領も没収となった。多くの家来は路頭に迷い、家族は恥辱のなかを生きていかなければならない。
武士の風上にもおけない玄蕃の行動を乙次郎は快く思っていなかったが、その人柄に触れるにつけ、なぜ玄蕃が腹を切らなかったのかが益々疑問に思えてくる。
乙次郎は玄蕃の中に2人の玄蕃がいるように感じる。
玄蕃は町人のような軽い言葉を使い、旅先で出会う人々と親しくなり、お節介なのか、人がいいのか、苦境に立たされている人たちの困りごとに首を突っ込んで解決してゆく。
一方で、旗本の顔になった時の玄蕃は威厳があり、凛としていて、いかにも武士らしい。
こう書くと、「水戸黄門」か「遠山の金さん」のような痛快時代劇を思い浮かべるかもしれないが、さにあらず。確かに笑える部分もあるが、なかなか重いテーマを内在した作品だった。
人が人を裁くことはできるのか。「法」とはなにか。
市中引き廻しの上磔(はりつけ)のような惨(むご)たらしい処刑方法は本当に必要なのか。仇討(あだうち)は私刑ではないのか。現代で言えば警察官のような仕事をしている乙次郎は様々な疑問にぶつかる。
この時代の武士は人を斬ったことも、戦(いくさ)をしたこともない人がほとんどで、ただの役人といっても過言ではない。役目は基本的に世襲で、旗本の中には何の役目もなく、ただ俸禄をいただいて豊かな暮らしをしている家もあるという。しかし、その武士の身分は遥か昔の戦国時代から引き継がれたもの。硬直化した身分制度の中で、世の中の仕組みが金属疲労を起こしている。
乙次郎は同心の家の次男で剣術と勉学に励み、白羽の矢が立って与力の家の婿養子となった。婿としての気苦労はあるにせよ、同じ部屋住み(次男以下で家督を継げない男子)たちが羨むような出世だ。玄蕃は武士としてはものすごく格上だが、乙次郎は押送人としての立場上、気圧されないように努めている。玄蕃は30代半ばくらいの年齢だろうか。人生経験も豊富で思慮深い玄蕃が相手では、自然と師弟関係のように玄蕃が導くような格好になってしまう。
1860年という時代設定が絶妙だ。桜田門外で井伊大老が水戸浪士らに暗殺された年で、激動の時代が目の前まで迫っている。明治元年は1868年。あと8年で260年続いた江戸時代が終わる。この旅の後、武士という身分に窮屈さと理不尽を感じている玄蕃と乙次郎が新しい時代をどう生きるのか、そんなことも想像させる。
【奥森 広治】