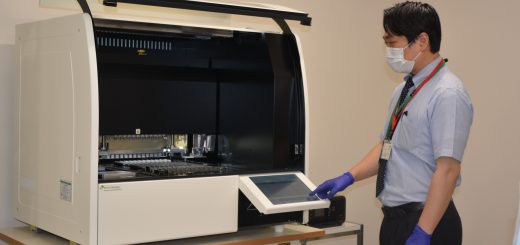本よみ松よみ堂
原田マハ著『たゆたえども沈まず』

幻冬舎文庫 750円(税別)
ゴッホを献身的に支えた弟、浮世絵との奇跡の出会い
生きている時には絵が全く売れず、死後、その作品が高く評価されるようになったという悲劇性から何度も映画化されたフィンセント・ファン・ゴッホの生涯。この作品では、フィンセントの才能を信じて献身的に支えた画商の弟・テオ(テオドルス・ファン・ゴッホ)と日本人画商・林忠正と加納重吉との交流を中心に描いている。
「タンギー親父」という作品がある。画材屋のタンギーの肖像画で、背景には何枚もの浮世絵が描かれている。日本人からすると、なぜここに浮世絵が?と思う作品である。
明治時代、パリで行われた万博をきっかけに欧州で日本美術のブーム「ジャポニスム」が起きた。テオは浮世絵がきっと兄の絵にいい影響を与えると確信して、忠正や重吉を通して浮世絵を手に入れてフィンセントに見せる。実際にフィンセントは多くの浮世絵をコレクションしていたようだ。
タンギーは人のいい画材屋で、フィンセントがためた絵の具やカンバスの代金の代わりに肖像画を描いてもらう。タンギーの優しい人柄がにじみ出たような明るい色彩の作品で、後ろに飾られた浮世絵のせいで、全体的ににぎやかな作品になっている。
タンギーは店で画材のほかに新進のポスト印象派の画家たちの絵を売っていた。
欧州の芸術の中心地だったパリで権威を持っていたのはフランス芸術アカデミーの画家たちが描く神話や歴史に題材を求めて、完璧な人物像と風景を描いた絵だった。テオが勤める「グーピル商会」が扱う絵もアカデミーの画家が描いた絵だったが、テオは印象派の画家たちが描く絵に心ひそかに惹かれていた。画家の「印象」によって描かれた絵は、まだ芸術として認められておらず、特にアカデミーの画家たちからは目の敵にされていた。テオも表立っては印象派の画家に共感していることを言えなかった。
フィンセントが印象派に影響を受けて絵を描き始めたのはそんなころで、画家として活動したのは37歳で亡くなるまでの約10年間という短い間だった。
芸術として認められていなかったという点では、日本における浮世絵も同じで、まるで新聞紙のように物を包むときの紙などとしてぞんざいに扱われていた。林忠正はこの浮世絵を安く買い入れ、パリのブルジョワたちに高値で売っていた。
忠正の仕事を手伝うために日本から呼ばれた重吉は架空の人物で、史実とフィクションをつなげる役割をしているのだと思う。
物語の中で、重吉はテオと親しくなり、テオとフィンセント、忠正を引き合わせることになる。
19世紀後半のフランス・パリで印象派の画家たちと日本の浮世絵は運命的に出会い、化学反応を起こして、新しい芸術が生まれた。そんな奇跡のような瞬間が描かれている。
テオとフィンセントの間には多くの書簡が残されている。
ゴッホ家はオランダ人で、家計を支えているのはテオだけだった。テオはフィンセントに生活費や画材を購入する金を与えていたが、フィンセントは画材代も飲んでしまうようなどうしようもないところがあった。タンギーの肖像画を描いたのも、テオが画材代として与えた金で酒を飲んでしまったからだった。そんなフィンセントの存在は時にテオの重荷にもなっただろうが、テオはフィンセントを見捨てることなく献身的に支えた。まるで自分の半身を支えるように。
読み終わると、表紙に使われている「星月夜」(1889年、ニューヨーク近代美術館蔵)の絵に込められた思いが分かり、改めて見たくなった。【奥森 広治】